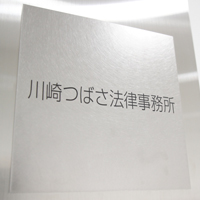交通事故が発生した場合、損害額について事故の加害者と被害者の間で話し合いを行い、解決を目指していくケースがあります。
お互いに合意すると示談成立となりますが、実際には不利な条件を提示されたり、交渉に時間がかかったりする場合も少なくありません。
そのため、示談を行うにあたり「何をすればいいの?」「示談して問題ない?」などの疑問や不安に感じる方は多いのではないでしょうか。
示談で失敗しないためには、正しい知識を身につけることや、弁護士への依頼がおすすめです。この記事では、示談交渉で話し合いする内容や交渉の流れ、注意点を紹介します。
Contents
交通事故の示談について
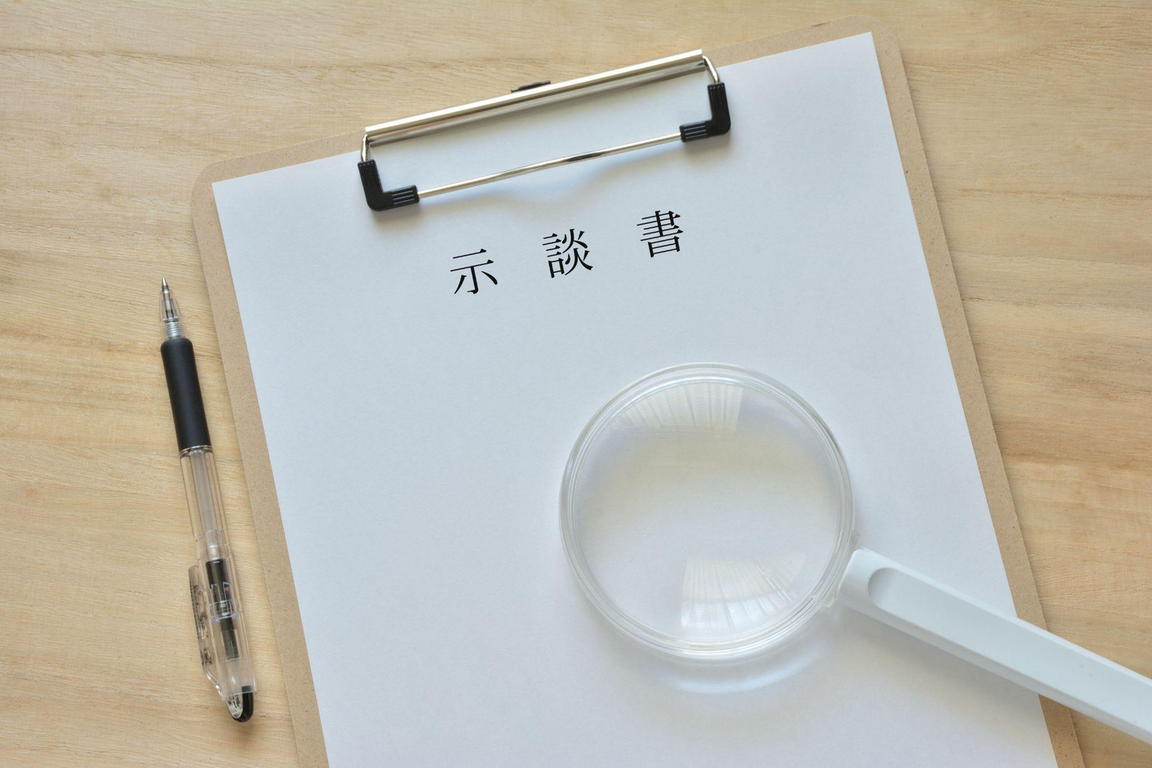
はじめに、交通事故の示談について詳しく解説します。
交通事故の示談とは
交通事故の示談とは、過失割合や慰謝料などの賠償内容に関して、裁判ではなく事故の加害者と被害者で話し合って決めることです。
交通事故の裁判には、加害者の刑事責任を問う刑事裁判や、加害者に損害賠償を請求するための民事裁判があります。
損害賠償を民事裁判で争うことになると、裁判費用や弁護士費用が多くかかるため、交通事故の場合は示談による早期解決を目指すのが一般的です。
示談にかかる期間は事故の状況によって異なり、後遺症が残る事故や死亡事故の場合、交渉が長期化しやすくなります。
なお、示談が成立すると合意内容を後から撤回することはできません。その理由は、示談成立には、その内容に法的拘束力が発生するためです。
そのため、示談内容に少しでも不明点があれば安易に合意してはいけません。
交通事故の過失割合について
交通事故の過失割合とは、加害者と被害者それぞれの事故の責任を数字で表したものです。6対4のように数字で、数字が大きいほど過失が大きいことを意味します。
交通事故では、どちらか一方だけ悪いということはなく、被害者にも過失が付く場合が多いです。
法律上、加害者だけに全ての損害を負担させることは適切ではないため、被害者の過失分が損害賠償金から減額されます。
過失割合は示談交渉時に確定させて、被害者と加害者の保険会社の交渉で決めていくのが一般的です。
加害者側の保険会社が提示する過失割合に納得できる場合は、その過失割合を前提として損害賠償金額についての協議が進みます。
一方、納得できない場合は示談が成立するまで協議を続けることになり、協議を重ねても双方が合意できなければ裁判となります。
示談金に含まれるもの
交通事故の示談金に含まれるものは次の通りです。
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 慰謝料
- 修理費
- 逸失利益
人身事故の実害部分は治療費、通院交通費、休業損害、精神的苦痛に対しての慰謝料です。交通事故がなければ、本来得られた収入にあたる逸失利益も請求できます。
示談金総額の相場は、事故の案件や重さ、個別の事情によって異なるため、一概にどれくらいになるとはいえません。
しかし、相場の計算については自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準などがあり、これらに基づいて計算を行うことで大まかな示談金を算出できます。
この中で最も高額なのは、裁判の算定にも使われる弁護士基準です。
示談金、損害賠償金、慰謝料の違い
示談金とは示談によって決定された賠償金のことであるため、示談によって損害賠償金や慰謝料が決定した場合は示談金となります。
そのため、調停や裁判により損害賠償金や慰謝料が決定された場合は示談金とはいえません。
なお、治療費や通院交通費、逸失利益などは損害賠償金に該当しますが、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などは慰謝料に該当します。
交通事故の示談交渉の流れ

交通事故が発生した場合、示談交渉はどのように進んでいくのでしょうか。ここでは、交通事故の示談交渉の流れを解説します。
事故の発生
交通事故が発生したら、まずは警察に通報しなければなりません。どれだけ軽い事故でも、警察への報告は道路交通法に規定された事故当事者の義務です。
警察への報告を行わないと被害者側も罰則を受ける可能性があるだけでなく、交通事故証明書の発行もできません。交通事故証明書は、保険会社に保険金を請求する際に必要です。
警察への通報が終わったら事故の状況を確認してカメラにも記録し、加害者の氏名、連絡先、ナンバーも控えておくとよいでしょう。
治療
交通事故に遭ったあとは、早めに病院に行って診察を受けておく必要があります。
事故による症状は事故直後に表れるとは限らないため、事故から間を空けて受診すると、事故による症状かどうかの判断がつきません。
事故との関連性がないと判断されてしまうと、治療費の請求ができなくなる可能性があります。
示談交渉に必要となる診断書は医師しか発行できないため、交通事故で負傷した際には必ず病院で治療を受けてください。
なお、整骨院や接骨院では診断書の発行ができないため注意が必要です。
症状の診断
交通事故でケガをして治療を継続しても症状の改善が見込めない場合は、症状固定の診断を受けるまで続ける必要があります。
症状固定や完治すると損害額が確定するため、それから示談交渉へと進む流れです。通院や治療は忙しくても途中で途切れさせず、最後まで通院することが重要となります。
完治する前に通院や治療をやめてしまうと、そのケガが本当に交通事故によるものかどうかも疑われてしまうことがあるため注意が必要です。
後遺障害等級認定
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害によって生じた損害の賠償を請求できるため、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
後遺障害等級認定は、後遺障害にあたるかを判断し、14の等級に分類するための手続きです。
それぞれの等級には独自の基準があり、満たさなければその等級の後遺障害には認められません。後遺障害等級認定は、適切な賠償を受けるために必要です。
後遺障害等級認定を受けなければ、後遺障害を根拠とする損害への賠償である後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求ができません。
認定される等級によって賠償金の金額は変動するため、適切な賠償を受けるためには、症状に見合った正しい等級認定を受ける必要があります。
示談交渉の開始
交通事故による損害が確定し、示談金の計算ができるようになったら交渉を始められます。
示談交渉を行う場合、加害者側の立場として交渉するのは本人ではなく、加害者が加入している任意保険会社の示談交渉担当員です。
相手に示談案を提示されても、その内容に納得できないのであれば合意しなくても問題ありません。相場の調査や弁護士に依頼するなどして、納得できる条件で合意しましょう。
なお、示談交渉には交通事故証明書や診断書、実況見分調書、事故発生状況報告書など、さまざまな書類が必要となります。必要書類を調べ、早めに用意しておきましょう。
成立~示談金の支払い
示談が成立してから、数日〜2週間程度で示談金が振り込まれます。
加害者と被害者の双方で示談金の金額の合意が取れ、示談書を作成した後に、加害者が加入している任意保険会社から示談金が支払われます。
任意保険会社が示談交渉の窓口になっている場合であれば、示談金の支払いについて問題になるケースはほとんどありません。
しかし、加害者本人と交渉する際には注意が必要です。示談が成立してお金が振り込まれない場合もあるため、不安がある場合は弁護士のサポートを受けるのもよいでしょう。
交通事故の示談交渉の注意点

交通事故の示談交渉を行う際には、どのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。ここでは、示談交渉で知っておきたい注意点を解説します。
その場で示談交渉をしない
交通事故が発生した場合、加害者からその場で示談交渉されることもありますが、絶対に交渉を行ってはなりません。
その場で示談交渉してはならない理由としては以下が挙げられます。
- 道路交通法違反で罰則を受ける可能性がある
- 保険金請求や示談金請求で必要な書類が作れない
- 交通事故直後は正確な示談金がわからない
- 示談は口頭でも成立する
加害者がその場で示談交渉したがる理由は、免停などの行政処分を受けたり、本来よりも少ない示談金で済んだりするためです。
また、仕事や用事などで急いでいて、早く済ませたいという場合もあるでしょう。
いずれにしても、その場での示談交渉は被害者に不利になります。加害者に示談交渉を持ちかけられても応じず、まずは警察を呼びましょう。
示談交渉は人身事故で行う
示談交渉は人身事故で行いましょう。
なぜなら、交通事故が物損事故で処理されてしまうと実況見分を行わないため、過失割合で争いになった場合に証拠が得られず立証が難しくなるためです。
物損事故だとケガをしていても軽いケガと判断されてしまい、十分な示談金を受け取れない可能性があります。
物損事故で処理されてしまった場合は、管轄の警察署で人身事故への切り替えを行いましょう。
保険会社の言葉を鵜呑みにしない
示談交渉は、加害者側もできるだけ有利な条件で合意しようとするため、任意保険会社の言葉を鵜呑みにしないように注意しましょう。
最初に提示される示談金も本来受け取れる金額ではなく、被害者にとって不当に低いケースがあります。
任意保険会社は支払額をできるだけ抑えるために、低額の示談金である自賠責基準や任意保険基準で解決を図ろうとします。
加害者側の言い分を鵜呑みにしないためにも、被害者自身が示談金の仕組みや相場を知っておくことが大切です。
もしくは弁護士に依頼して、不利にならないように交渉を進めてもらいましょう。
示談成立後は撤回できない
示談成立後は、示談内容を撤回できないため注意しましょう。
示談書にサインして判を押すと、示談内容に合意したことになります。示談書には、「被害者はこれ以上の損害賠償請求をしない」という旨の文言が記載されている場合がほとんどです。
そのため、成立した示談をやり直すことは基本的にできません。
ただし、後から後遺障害が発覚したり、示談成立の過程でトラブルがあったりした場合は、示談後の追加請求や示談の撤回ができるケースもあります。
このような場合は、弁護士に相談して対応してもらう必要があります。
時効に気をつける
交通事故の示談では、加害者に対して損害賠償請求できる権利に時効がある点に注意が必要です。
交通事故の時効は物損事故なら3年、人身事故や死亡事故なら5年が期限となります。時効が過ぎてしまうと、損害賠償請求権を失ってしまうため注意しましょう。
交通事故が発生してから適切に治療や交渉を進めていけば、時効についてそれほど心配する必要はありません。
時効を気にして焦って示談すると、不満の残る結果になりやすいため、示談には納得できる条件で合意することが大切です。
ただし、示談交渉が難航したり、交渉のタイミングが遅かったりすると時効が迫ってくる場合もあります。
示談交渉が難航しそうな場合は、弁護士に依頼して示談交渉を進めてもらうと安心です。
まとめ
この記事では、交通事故の示談や交渉の流れ、注意点を解説しました。
交通事故の示談交渉は合意してしまうと基本的に撤回できないため、慎重に進めていく必要があります。
加害者側は任意保険会社の担当者が示談交渉する場合が多く、正しい知識がなければ、不利な条件で合意させられるケースも少なくありません。
交通事故の示談で失敗しないためには、示談交渉に強い弁護士に依頼し、交渉してもらうのがおすすめです。
交通事故の示談交渉なら、川崎つばさ法律事務所にお任せください。
任意保険会社が提示する金額に納得できない、示談交渉に不安があるなど、さまざまな不安やお悩みにお応えいたします。
また、後遺障害等級認定を有利にする医学的知識も保有しています。
当事務所の相談対応は平日・土日含め20時まで対応しており、相談は早いほどサポートの幅が広がるため、ぜひお早めにご相談ください。