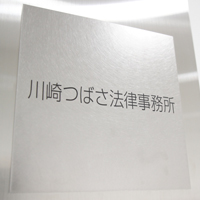離婚する際、当事者同士の話し合いでどうにもならない場合は、離婚裁判によって解決を図る必要があります。
離婚裁判を検討している方のなかには、「離婚裁判にかかる期間が気になる」「費用が知りたい」という方が多いのではないでしょうか。
離婚裁判をスムーズに進めていくためには、弁護士へ早期に相談するのも方法の一つです。この記事では、離婚裁判の期間がどれくらいかかるかや、流れを短縮するポイントを紹介します。
Contents
離婚裁判の平均期間

ここでは、離婚裁判にかかる期間を解説します。
統計データから見る離婚裁判の期間
裁判所が発表している2023年1月~12月の人事訴訟事件の概要によると、離婚裁判の審理期間の平均は15.3ヵ月です。
裁判途中に和解するなど早期終了したパターンを除くと、平均19.9ヵ月かかっています。ケースによって異なるものの、離婚裁判の期間の目安は約1〜2年です。
なお、離婚裁判は裁判所の判決によって強制的に離婚を目指す手続きとなります。協議離婚や調停離婚で離婚ができなかった場合に、離婚を求めるための最終手段となるのが離婚裁判です。
離婚裁判が長期化するケース
離婚裁判は裁判手続きそのものに時間がかかることに加え、すでに話し合いで解決できない関係性になっているため長期化するケースが多いです。
離婚裁判は他人が相手ではなく、将来を共にしようと決めたパートナーと離れるために行います。
そのため、気持ちのコントロールが難しく、裁判が長期化すると当事者は長期にわたって精神的なストレスを受けることになります。
離婚裁判が長期化してストレスが大きくなると、「不利な条件でも早くストレスから解放されたい」という心理状態になりがちです。
しかし、妥協したことによって離婚後に後悔する可能性もあるため、納得できる条件で離婚するのが望ましいでしょう。離婚裁判を長期化させないためにも、早めの対策が必要です。
離婚裁判の流れと段階ごとの期間

離婚裁判はどのように進んでいくのでしょうか。ここでは、離婚裁判の流れと段階ごとの期間を解説します。
離婚調停から裁判への移行
離婚裁判では、まず離婚調停で話し合いをしなければならないというルールがあります。
離婚調停とは、家庭裁判所において夫婦間の問題について話し合う手続きです。調停員と呼ばれる人が中心となり、夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与などの離婚条件について調整します。
離婚裁判と同じく裁判所を介して離婚を進めますが、離婚裁判は裁判官が判断を下すのに対し、離婚調停はあくまでも話し合いで解決を目指す点が違いです。
離婚調停で話し合いがまとまらず調停が不成立で終了すると、その後に離婚裁判の提起ができます。
訴状提出から第1回口頭弁論まで
離婚裁判を提起するにあたって、まずは当事者や離婚の理由などを記載した訴状を家庭裁判所に提出しなければなりません。
提出先となるのは、夫婦どちらかの所在地を管轄する家庭裁判所か、離婚調停を行った家庭裁判所になります。なお、弁護士に依頼している場合は、訴状提出に必要な書類は弁護士が管理します。
なかには、自分自身で訴訟を行う場合(本人訴訟)もありますが、本来勝てるはずの訴訟で負けてしまう可能性があり、リスクを伴う点には注意しましょう。
訴状が認められると、裁判所から第1回口頭弁論の期日が知らされます。第1回口頭弁論が開催されるのは、訴状を提出してから1ヵ月程度です。
口頭弁論の進行と期間
第1回口頭弁論では、原告が作成した訴状を裁判官が読み上げ、次いで被告が作成した答弁書を読み上げて問題の争点を整理します。
争点の結果に基づき、原告がその事実を証明する証拠を提出し、被告からは否定する証拠が提出され、このやりとりは何回か行われるのが一般的です。
証拠提出の際には、書類だけでなく証人が出廷し、法廷で離婚原因を述べる場合もあります。原告の主張が確かに事実であったかどうかを裁判官が認定します。
なお、第1回口頭弁論で判決が言い渡されることは少なく、第2回口頭弁論に進むのが一般的です。それでも判決がまとまらない場合は、第3回、第4回口頭弁論に進む場合もあります。
判決までの期間
第1回口頭弁論から判決までの口頭弁論回数は10回以下が多く、1ヵ月に1回程度のペースで行われるため、判決までには1年ほどかかります。
離婚裁判の判決が確定したら、10日以内に判決の謄本と判決確定証明書を添え、本籍地または住所地の市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。
なお、離婚裁判で離婚が成立しなかった場合は控訴することもできます。
離婚裁判が長期化する原因

離婚裁判の期間は、争点や証拠の有無などによって大きく異なります。ここでは、離婚裁判が長期化する主な原因を解説します。
争点が多い場合
争点が多いと離婚裁判は長期化しやすくなります。離婚裁判では、慰謝料、面会交流、年金分割など、さまざまなことを話し合って決めなければなりません。
双方が離婚の条件を譲り合う場合は早期解決できますが、お互いが譲り合わなければ、一つひとつの問題について時間をかけて解決していく必要があります。
財産分与や親権の問題
離婚裁判では、財産分与や親権を巡ってトラブルが大きくなり、長期化するケースが多くあります。
財産分与とは、結婚してから別居するまでの間に蓄えた財産を双方で分ける制度です。親権は未成年の子どもを養育し、財産管理や法律行為を代理したりする権利を指します。
財産分与や親権についてお互いに主張があり対立すると、証拠や資料集めが必要となり、時間がかかるというわけです。
そのため、複数の財産がある場合や子どもがいる場合は、離婚裁判も長期化しやすくなります。
証拠不足や立証の困難さ
離婚裁判では事実に基づいて審議が行われるため、主張を裏付ける証拠がなければ、請求を認めてもらうことはできません。
裁判官が請求事項を判断するためには証拠が必要であり、少ない場合は証拠収集に時間がかかります。
証拠収集をするために証人の証言を得たり、新たな証拠を探したりする必要があるため、検討を進めるための時間もかかるでしょう。
それでも主張を裏付けるだけの十分な証拠がなければ、判決にも納得ができず、離婚裁判がさらに長期化する可能性が出てきます。
離婚裁判を早期に終わらせるためのポイント

離婚裁判を長期化させないためには早めの対策が必要です。ここでは、離婚裁判を早期に終わらせるためのポイントを解説します。
証拠の準備と整理
離婚裁判を早期に終わらせるためには、十分な証拠を準備し整理しておくことがポイントです。
例えば、離婚の原因が相手の不貞行為の場合は、不貞行為を認める発言の録音データ、DVであればDVの被害状況を記した日記や動画、音声データ、診断書などが証拠となります。
なお、証拠を集めるなら離婚裁判が始まる前にしましょう。裁判が始まると相手も証拠集めに警戒するため、思うように証拠が集まらない可能性があります。
弁護士への相談と依頼
離婚裁判を円滑に進めていくためには、離婚問題に強い弁護士に早めに相談して依頼しましょう。早い段階から離婚問題に強い弁護士に依頼することで、問題が大きくなる前に早期解決を目指せます。
なお、離婚問題は夫婦関係の解消だけでなく、親権や財産分与、養育費など、さまざまな問題を解決しなければなりません。
離婚問題で大切なことは、これらを夫婦が納得できるように解決に導いていく交渉力や提案力です。そのため、離婚問題の解決実績が多い弁護士に依頼することが大切です。
和解の検討
離婚裁判を進めていくと、裁判官が和解案を出してくるため、納得できる内容であれば和解の方向で進めていくのもよいでしょう。
裁判官が提示する和解案に基づいて離婚することを、和解離婚といいます。
裁判所が離婚の成立と離婚の条件について和解調書を作成して調書に押印し、その調書を役所に提出することで離婚が成立します。
離婚裁判では判決というイメージも大きいですが、実際には和解離婚が成立するケースも多いです。
和解離婚は離婚裁判の早期終了を目指すことができ、判決で離婚するよりお互いにとってよい条件で離婚しやすいメリットがあります。
離婚裁判にかかる費用

離婚裁判を行うにあたって、事前にどれくらい費用がかかるか調べておく必要があります。ここでは、離婚裁判にかかる費用を解説します。
裁判費用の内訳
離婚裁判そのものにかかる費用は2〜3万円です。費用は、主に収入印紙代と郵便切手代、戸籍謄本取得費用となります。
離婚のみの場合は1万3,000円で、慰謝料や親権、財産分与などの判決も求めるなら追加料金が発生します。また、裁判書類を送る際に利用される郵便切手代は約6,000円が相場です。
戸籍謄本取得費用は、450円となります。
弁護士費用の目安
離婚裁判にかかる費用相場は約70〜120万円程度です。
弁護士に依頼する際にかかる費用としては、着手金と成功報酬があります。離婚裁判における着手金の目安は、約30〜70万円ほどです。
一方、成功報酬も約30~70万円が目安ですが、それ以外に相手から経済的利益を獲得した場合に、その利益の約10~15%ほどの費用が別途かかります。
上記以外にも、弁護士が裁判所に出向くための交通費や相談料が必要です。
弁護士費用の支払いが難しい場合は、法テラスを利用して弁護士費用を立て替えてもらうか、弁護士事務所によっては後払いや分割払いをしてもらうこともできます。
離婚裁判と他の離婚方法の比較

離婚の方法は、離婚裁判以外にもあります。ここでは、離婚裁判と他の離婚方法を比較していきます。
協議離婚との違い
協議離婚と離婚裁判の違いは、家庭裁判所が関与するかしないかです。
協議離婚とは、夫婦が話し合いをしたうえで離婚を成立させることです。夫婦の話し合いで離婚条件を決めますが、話がまとまらない場合は弁護士に依頼して進めていくとスムーズです。
また、合意内容が決まって離婚協議書や公正証書を残す際にも、弁護士に依頼すると法的に適切な書類を作成してもらうことができます。
夫婦の合意さえあれば離婚届を提出するだけであるため、早く簡単に離婚できます。
調停離婚との違い
調停離婚と離婚裁判の違いは、離婚成立を目指す過程において、話し合いで決めるか、判決で決めるかです。どちらも家庭裁判所で行われるという点では共通しています。
調停離婚は話し合いであるため、なかには「話し合いなら裁判所に行く必要はないのでは?」と思う方もいるでしょう。
しかし、当事者だけで話し合って離婚を決める場合だと、感情的になってうまく話し合いができなかったり、一方が話し合いに応じなかったりする場合もあります。
話し合いを円滑に進めていくために、家庭裁判所が中に入って離婚協議を進めていくのが離婚調停です。離婚調停で話がまとまらない場合は、離婚裁判となります。
まとめ
この記事では、離婚裁判の期間はどのくらいかかるかや、流れ、短縮のポイントを解説しました。離婚裁判は1~2年かかるのが一般的ですが、争点が多い場合はさらに長期化する場合もあります。
離婚問題が長期化すると、精神的なストレスも大きくなり、仕事やプライベートにも影響が生じる可能性があります。
離婚問題を早期に解決したい場合は、協議離婚や調停離婚の段階で合意を得るというのも方法の一つです。
また、離婚問題を円滑に進めていくためには、早い段階で弁護士に依頼し、準備を進めていくのもポイントです。
離婚問題のことなら、川崎つばさ法律事務所にお任せください。
当事務所は離婚協議、調停離婚、離婚裁判などを数多く経験してきており、さまざまな過去の事例に基づき、一人ひとりに最適なサポートができるのが強みです。
離婚をするかどうかまだ決めていない段階でも、まずはお気軽にご相談ください。