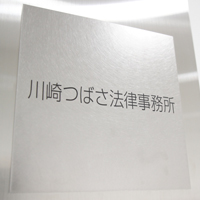遺言書には主に3つの種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。
遺言書の作成を検討しているものの、種類や特徴がわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺言の種類と特徴について詳しく解説します。
Contents
遺言とは

遺言は、自分の死後に財産をどのように分配するかを法的に有効な形で示すものです。
ここでは、遺言について詳しく解説します。
遺言を作成する目的
遺言を作成する主な目的は、相続人間のトラブルを防ぎ、円滑な相続を実現することです。
遺言があれば、被相続人の意思が明確になるため、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。また、法定相続分とは異なる分配を希望する場合や、特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合にも有効です。さらに、法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合にも遺言が必要となります。
遺言を作成することで、自分の意思を明確に示し、大切な人々に財産を適切に引き継ぐことができます。
遺言の法的効力
遺言は、法律で定められた方式に従って作成されれば、法的な効力を持ちます。
遺言の内容は法定相続分よりも優先されるため、被相続人の意思を尊重した相続が可能となります。ただし、遺留分を侵害する内容の場合、遺留分権利者から減殺請求を受けるケースも少なくありません。
また、遺言の内容が公序良俗に反する場合や、遺言能力がない状態で作成された場合は無効となることがあります。そのため、遺言を作成する際は、法的要件を満たし、適切な内容であることを確認することが重要です。
遺言書の基本的な種類

遺言書には主に3つの種類があり、それぞれに特徴があります。
ここでは、遺言書の基本的な種類について詳しく解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書くとともに日付と氏名を記載し、押印して作成する遺言書で、作成が簡単かつ費用がかからないのが最大の特徴です。
ただし、法的要件を満たさないと無効になるリスクがあるため、注意が必要です。また、遺言書の存在を相続人が知らない可能性や、紛失・隠匿のリスクもあります。
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要となりますが、2020年7月からは法務局での保管制度が開始されており、この制度を利用すれば検認が不要となります。比較的簡単な相続の場合や、急を要する場合に適している方法です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人の立会いのもと、証人2名以上の立会いで作成する遺言書です。法的な有効性が高く、原本が公証役場で保管されるため、紛失や隠匿のリスクがありません。
また、検認手続きも不要であり、公証人のサポートを受けながら作成できるため、法的な不備が生じにくいのも特徴です。ただし、作成には費用がかかり、遺言の内容を完全に秘密にすることはできません。
公正証書遺言は、最も確実な遺言方法とされており、財産が多い場合や相続人間でトラブルの可能性がある場合におすすめです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、公証人と証人2名以上の立会いのもとで手続きを行う遺言書です。
遺言の内容を秘密にできる点が最大の特徴です。ただし、自筆証書遺言と同様に、法的要件を満たさないと無効になるリスクがあります。
また、検認手続きが必要で、紛失や隠匿のリスクもあります。秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたい場合に適していますが、作成手続きが複雑なためあまり一般的ではありません。
遺言の内容を秘密にしつつ、法的な有効性を確保したい場合に検討する価値があります。
遺言書の種類ごとの作成方法
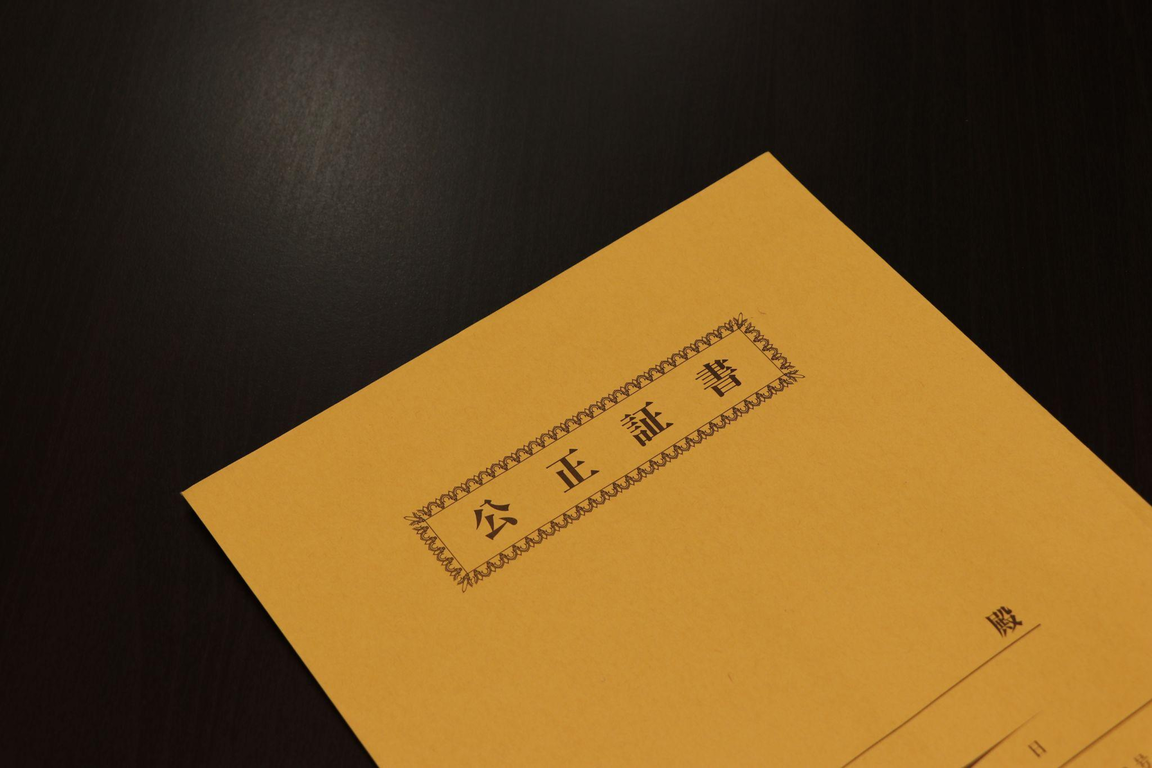
各遺言書の種類によって、作成方法が異なります。
ここでは、遺言書の種類ごとの作成方法について詳しく解説します。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、適切な項目を記載する必要があります。
自筆証書遺言の作成手順は以下の通りです。
- 遺言の全文を自筆で書く
- 日付を記入する
- 氏名を記載し、押印する
- 財産目録を添付する場合は、各頁に署名押印する
注意点として、パソコンやワープロの使用は認められません。また、加除訂正がある場合は、その箇所を特定し、訂正印を押す必要があります。
財産目録については、2019年1月13日以降はパソコン等で作成したものや通帳のコピーなどの添付が認められるようになりました。
自筆証書遺言は比較的簡単に作成できますが、法的要件を満たさないと無効になるリスクがあるため、慎重に作成することが重要です。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、公証人のサポートを受けながら作成できるため、法的な不備が生じにくいのが特徴です。
公正証書遺言の作成手順は以下の通りです。
- 公証役場に予約を入れる
- 必要書類を準備する(戸籍謄本、印鑑証明書など)
- 遺言の内容を公証人に伝える
- 公証人が遺言書を作成する
- 証人2名以上の立会いのもと、内容を確認し署名・押印する
公正証書遺言は、公証人が遺言能力を確認しながら作成するため、後々遺言能力が問題になるリスクも低くなります。費用はかかりますが、最も確実な遺言方法として広く利用されています。
秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできますが、法的要件を満たさないと無効になるリスクがあるため、注意が必要です。
秘密証書遺言の作成手順は以下の通りです。
- 遺言書を作成する(自筆でなくてもよい)
- 遺言書に署名し、押印する
- 遺言書を封筒に入れ、封印する
- 公証役場で、公証人と証人2名以上の立会いのもと手続きを行う
秘密証書遺言は、作成手続きが複雑なため一般的にはあまり利用されていません。遺言の内容を秘密にしたい場合は、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言も検討する価値があります。
遺言書の保管と検認手続き
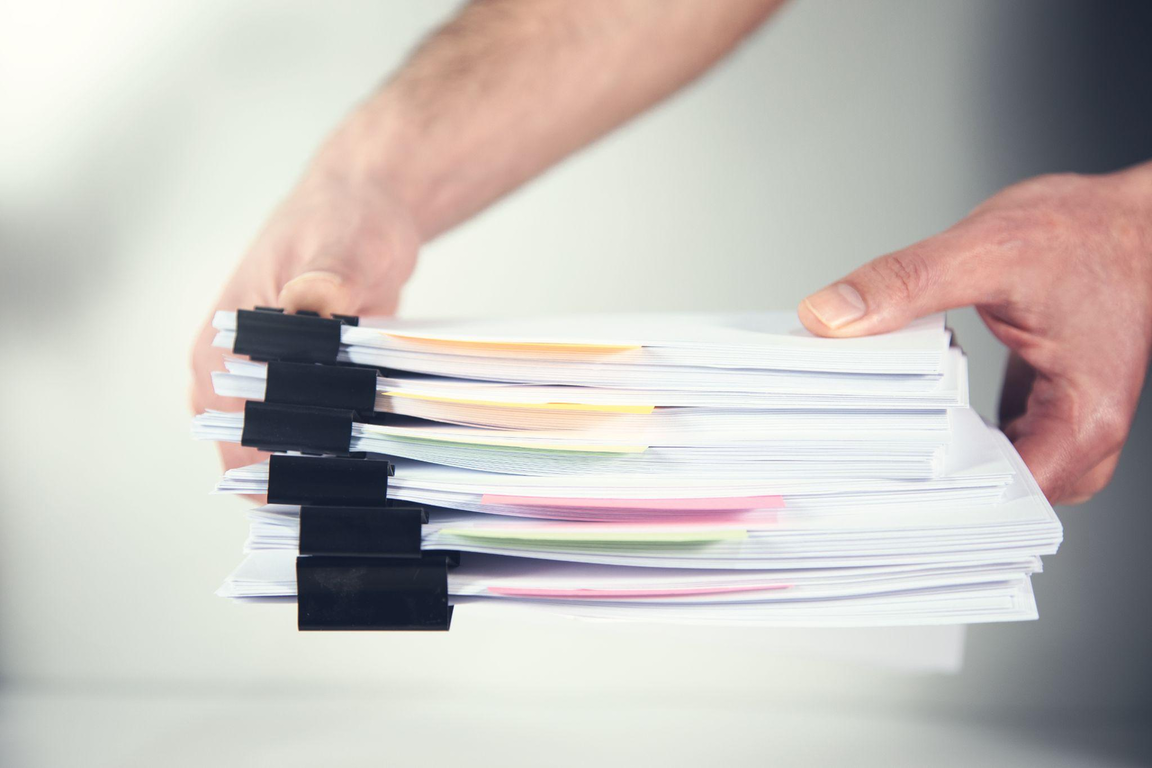
遺言書の保管方法と検認手続きは、遺言書の種類によって異なります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、従来は遺言者自身が保管する必要がありましたが、2020年7月から自筆証書遺言については法務局での保管制度が開始されました。この制度を利用すれば、検認手続きが不要となり、紛失や隠匿のリスクも軽減されます。
公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるため遺言者による保管は不要で、検認手続きも不要です。また、自筆証書遺言(法務局保管を除く)と秘密証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
検認を受けないと、遺言執行者や相続人が悪意または重大な過失で検認を怠った場合、損害賠償責任を負う可能性があります。
遺言書の種類の選び方

遺言書の種類は、状況に応じて適切なものを選ぶことが重要です。
ここでは、遺言書の種類の選び方について詳しく解説します。
状況別におすすめの遺言書
遺言書は、状況に応じて適切な種類を選択するのが望ましいです。
遺言書の種類に応じたおすすめケースは以下の通りです。
| 遺言書の種類 | おすすめのケース |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 財産が比較的少なく、相続人間の関係が良好な場合 |
| 公正証書遺言 | 財産が多く、相続人間でトラブルの可能性がある場合 |
| 秘密証書遺言 | 遺言の内容を秘密にしたい場合 |
状況に応じて適切な遺言書の種類を選ぶことで、より確実に自分の意思を伝え、相続トラブルを防ぐことができます。
自筆証書遺言は簡単で費用がかからないため、比較的単純な相続状況に適しています。公正証書遺言は法的な確実性が高いため、複雑な相続状況や争いの可能性がある場合に適しています。秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたい場合に適していますが、現在ではあまり利用されていません。
専門家への相談の重要性
遺言書の作成は、相続に大きな影響を与える重要な行為であるため、専門家への相談が非常に重要となります。
弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 法的に有効な遺言書を作成できる
- 税金面での最適な対策を立てられる
- 相続人間のトラブルを未然に防ぐことができる
- 遺言者の意思を正確に反映した遺言書を作成できる
専門家に相談することで、自分の状況に最適な遺言書の種類や内容を決定することができます。また、将来的な相続税の問題や、相続人間のトラブルを防ぐための助言も得られるでしょう。
遺言書の作成は一生に一度の重要な決断です。専門家のサポートを受けながら、慎重に進めることをおすすめします。
遺言書作成時の注意点

遺言書を作成する際には、いくつかの注意点があります。
ここでは、遺言書作成時の注意点について詳しく解説します。
遺言の無効となるケース
遺言を作成する際に一定の条件が満たされていないと、遺言が無効となる場合があります。
遺言が無効となる主なケースは以下の通りです。
- 法定の方式に従っていない場合
- 遺言能力がない状態で作成された場合
- 遺言の内容が公序良俗に反する場合
- 脅迫や詐欺によって作成された場合
自筆証書遺言の場合、形式的要件を満たさないと無効となるリスクが高いため、注意が必要です。たとえば、パソコンで作成したり、日付や氏名を書き忘れたりすると無効となる可能性があります。
また、遺言能力の有無が問題となることもあるため、高齢者や病気の方が遺言を作成する場合は、医師の診断書を添付するなどの対策を取ることも検討しましょう。
遺留分への配慮
遺言を作成する際は、遺留分への配慮が必要です。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分のことです。遺留分を侵害する内容の遺言を作成すると、遺留分権利者から減殺請求を受ける可能性があります。
遺留分に配慮した遺言を作成するためには、遺留分の割合を正確に把握し、遺留分を侵害しない範囲で財産を分配、もしくは遺留分の放棄を検討する必要があります。ただし、相続開始前の放棄は無効です。
遺留分への配慮は複雑な場合が多いため、専門家に相談することをおすすめします。適切な配慮を行うことで、将来的な相続トラブルを防ぐことができます。また、遺留分を考慮しつつ、自分の意思を最大限反映させた遺言書を作成することが重要です。
特殊な遺言の種類

通常の遺言方式以外にも、特殊な状況下で認められる遺言の種類があります。
ここでは、特殊な遺言の種類について詳しく解説します。
特別方式の遺言
特別方式の遺言には、危急時遺言、船舶遭難時の遺言、隔絶地遺言などがあります。
危急時遺言は、死亡の危急に迫った場合に、証人3人以上の立会いのもとで口頭で行う遺言で、船舶遭難時の遺言は船舶が遭難した際に証人2人以上の立会いのもとで行う遺言です。また、隔絶地遺言は伝染病などにより隔離されている場合に、証人2人以上の立会いのもとで行う遺言となります。
これらの特別方式の遺言は、通常の遺言方式ができない特殊な状況下でのみ認められ、一定期間内に家庭裁判所の確認を受ける必要があります。
特別方式の遺言は、緊急時の最後の手段として位置づけられており、可能な限り通常の遺言方式を利用することが望ましいです。
口授遺言
口授遺言は、遺言者が口頭で遺言の内容を述べ、それを証人が筆記する方式の遺言です。
口授遺言は、通常の遺言方式ができない緊急時の手段として位置づけられています。ただし、遺言者が普通の方式で遺言できるようになってから6ヶ月以内に死亡しなかった場合は、その効力を失います。
口授遺言は、あくまでも緊急時の対応策であり、可能な限り通常の遺言方式を利用することが望ましいです。
まとめ
遺言書には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。
遺言書の種類を選ぶ際は、自分の状況や目的に応じて適切なものを選択することが重要です。また、遺言書の作成は相続に大きな影響を与え、遺留分への配慮や無効となるケースを避けるなど、注意点も多くあります。
遺言書の作成は、将来の相続トラブルを防ぎ、大切な財産を確実に引き継ぐための重要な手段です。専門家のサポートを受けながら自分の意思を明確に示す遺言書を作成することで、相続人の方々の負担を軽減し、円滑な相続を実現することができます。
遺言書の作成や相続に関する法的な問題について、専門的なアドバイスが必要な場合は、『川崎つばさ法律事務所』にご相談ください。
当事務所では、経験豊富な弁護士が、遺言書の作成から相続問題の解決まで、幅広くサポートいたします。
遺言の作成に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。