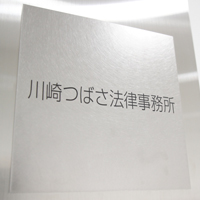「弁護士に依頼したいけど費用が高そう」このようなイメージで、相談できないという方もいるのではないでしょうか。
弁護士に相談や依頼する場合は、相談料をはじめ、着手金や成功報酬、実費など、さまざまな費用が発生します。
実際にかかる弁護士費用は依頼内容によって相場があるため、事前に把握しておけば見積もりを提示された場合に妥当性の判断がしやすくなるでしょう。
また、費用が支払えない場合は立替制度や分割払いなどの方法もあるため、支払える費用を持ち合わせていないからと諦める必要はありません。
この記事では、弁護士費用の相場や内訳、安く抑えるポイントを紹介します。
Contents
弁護士費用の相場

法律問題を弁護士に相談する際には、さまざまな費用が発生します。ここでは、弁護士費用の相場を解説します。
弁護士費用の取り決めについて
弁護士報酬基準は2004年4月に廃止され、現在は各弁護士が自由に報酬を設定できるようになっています。
以前は弁護士が所属する弁護士会が報酬会規を制定していたため、個々の弁護士が自由に費用を設定することはできませんでした。
制度が改定されてからは弁護士がそれぞれ費用を設定できるようになったため、依頼する弁護士によってかかる費用は異なっています。
しかし、弁護士報酬基準は長年にわたって基準として用いられたこともあり、これを参考にして報酬を決めているところも多くあります。
離婚問題の費用相場
離婚問題の費用相場は、着手金と成功報酬を含め、協議離婚は約50〜70万円、離婚調停は約70〜90万円、訴訟は約90〜110万円です。
弁護士に離婚問題を依頼する場合、「協議離婚」「離婚調停」「訴訟・裁判」に進んでいくのが一般的な流れとなります。
離婚協議であれば弁護士費用の相場は約50〜70万円ですが、調停や訴訟が必要になると、その分だけ費用も高くなります。
なお、協議離婚から調停や訴訟に発展する場合、追加の着手金については安くなるケースがほとんどです。
しかし、養育費や財産分与、不貞行為の調査や慰謝料請求のように、依頼が多岐に渡ると費用もそれだけ多くかかるため、事前に確認しておく必要があります。
交通事故問題の費用相場
交通事故問題の費用相場は、着手金は約20〜50万円、成功報酬は経済的利益の約5〜20%です。経済的利益とは、弁護士が介入したことによって発生した利益を意味します。
交通事故では、弁護士の介入によって賠償金を得られる場合があり、その金額によって成功報酬も変わってくるのが一般的です。
しかし、被害者が途中まで示談交渉を進めていた場合、弁護士が介入したことによって増額された金額を経済的利益として計算する場合もあります。
経済的利益がなければ成功報酬は発生せず、着手金のみになるケースもあります。
債務整理問題の費用相場
債務整理の費用相場は、任意整理だと債権者1社あたり2〜10万円、自己破産は約30〜70万円、個人再生は約50〜70万円です。
債務整理は、借金の減免により返済の猶予を得るために行う手続きを指します。
しかし、債務整理問題は借金に関する問題であるため、なかには「弁護士費用を用意できない」という方もいるでしょう。
このような場合は、分割払いや後払い、法テラスによる立替制度などを利用できます。
なお、借金問題を弁護士に依頼すると、すぐに借入先への返済をストップできるため精神的な負担も軽減できます。
遺産分割問題の費用相場
遺産分割問題の費用相場は、着手金が約15〜55万円、成功報酬が経済的利益の約5〜20%です。
遺産分割問題では、依頼した当人が費用を負担することになります。相続人のうち1人が依頼する場合はその人が負担し、数人が共同して依頼する場合は数人で分割する形です。
なお、調停や審判にまで発展する場合、費用はさらに高額になるケースもあります。
労働問題の費用相場
給料の未払いや労災などの労働問題の費用相場は、着手金が約10〜60万円、成功報酬が経済的利益の約5〜20%です。
労働問題のトラブルを弁護士に依頼することで、従業員からの訴えを聞かなかった企業も言い逃れができなくなります。
また、企業との交渉に戦略を立てて計画的に進めてもらうことも可能です。時間的・精神的な負担が軽減され、より有利な条件で問題解決を図ることができます。
インターネットトラブルの費用相場
誹謗中傷の削除依頼や開示請求などのインターネットトラブルの費用相場は、着手金と成功報酬金を合わせて約30〜100万円です。
誹謗中傷問題で損害賠償請求を行う際は、弁護士と共に交渉や訴訟手続きを進めていく必要があります。
この場合、弁護士費用は訴訟額や事件の難しさによって変わり、着手金が約50〜100万円、成功報酬が経済的利益の約10〜20%となります。
弁護士費用の内訳

弁護士に依頼する場合、どのような費用が発生するのでしょうか。ここでは、弁護士費用の内訳を詳しく解説します。
相談料
弁護士に依頼する場合は、契約の前段階で法律相談料が発生します。相談料は30分5,500円程度で設定されており、初回は無料相談できるケースが多いです。
その後、弁護士に正式依頼してからは委任契約書に記載された弁護士費用以外はかからないため、別途で相談料が発生することはありません。
相談料を抑えるためには、何度も相談するのではなく、事前に要点をまとめておいて相談回数を減らすのがコツです。
発生した事案については時系列に沿ってメモにまとめておき、役立ちそうな証拠や書類はすべて用意しておきましょう。
また、トラブルが発生した場合は早めに相談すると、大きな被害が出る前に解決できる可能性も高くなります。
着手金
弁護士に依頼する場合の費用として、依頼を受けた案件の弁護活動に着手する際にかかる着手金が挙げられます。
弁護士は依頼主から着手金を受け取った後、弁護活動に着手するのが一般的です。
弁護活動への対価となるため、途中解約や問題を解決できなかった場合に返金されることはありません。
また、着手金はトラブルの対象となる経済的利益の額や事件の規模、処理に必要となる執務量により変わってきます。
近年は着手金無料を掲げる弁護士事務所も増えていますが、注意が必要です。
着手金無料でも、その他にかかる経費はすべて有料だったり、成功報酬が相場よりも高額に設定されていたりする場合もあります。
弁護士費用は着手金だけではなく、成功報酬や経費など総額で判断することが大切です。
成功報酬
弁護士に依頼する際の成功報酬とは、トラブルが解決した後に発生する料金のことです。名前の通り、弁護士のトラブル処理が成功した場合にのみ発生します。
例えば、労働問題で100万円の給料未払いを巡って訴訟を起こした場合、請求が認められると成功報酬が発生し、認められないと発生しません。
成功報酬の額は成功の度合いに応じて算定され、一般的にはトラブル解決によって得られた経済的利益の額に一定の費用をかけて算定されます。
実費、日当
弁護士に依頼する場合は、着手金や成功報酬以外に実費や日当などの費用が発生する場合もあります。
実費は交通費や郵送費、戸籍や登記簿の取り寄せ費用で、日当は弁護士が業務のために事務所所在地から移動することにより、時間的に拘束される際に支払われる費用です。
実費や日当はトラブルの内容によって大きく変わります。弁護士が何度も遠方に足を運ぶ必要がある場合は、大きな支出になる場合もあるため注意しましょう。
実費や日当の費用が気になる場合は、弁護士への相談時に確認しておくと安心です。
手数料
弁護士に支払う手数料とは、当事者間に争いのないケースで事務的な手続きを依頼する際に発生する費用です。
原則として、必要な書面を作成したうえで、数回程度弁護士が裁判所とやりとりをすると済むような案件となります。
例えば、契約書や遺言などの書類作成、会社設立、登記にかかる費用などです。
弁護士費用を安く抑えるポイント

ここでは、弁護士費用を安く抑えるポイントを解説します。
できる限り早い段階で相談する
弁護士費用を安く抑えるためには、トラブルの初期段階で弁護士に相談することが重要です。
話し合いがこじれて当事者だけでは収拾がつかないほど争いが複雑になってくると、解決しなければならない問題が多くなっていきます。
この段階になるとお互いの考えが衝突してしまい、裁判に移行するしかないという状況にもなりかねません。
事件が長引いてしまうだけでなく、弁護士の対応時間も多くなり、結果的に弁護士費用が高くなってしまう可能性があります。
特に、権利やお金に関係するトラブルは複雑化しやすいため、早期に相談して問題解決を図ることが大切です。
弁護士保険に加入しておく
弁護士保険とは、弁護士に仕事を依頼した際にかかる費用を補償してもらえる保険です。
法の力を借りて問題を解決するためには弁護士の力が必要である一方、依頼する場合は数十万円〜数百万円の費用が発生する場合もあります。
このような場合、弁護士保険に加入しておくと費用を抑えることが可能です。
弁護士保険は月々数百円から数千円と安いため、トラブルに備えて事前に保険に加入しておくのもよいでしょう。
弁護士費用の立替制度を活用する
弁護士費用が払えない場合、法テラス(日本司法支援センター)の立替制度を利用するのも一つの方法です。
法テラスとは、国によって設立された法的トラブルを解決するための総合案内所で、立て替えてもらった費用は最終的に分割払いで返していきます。
経済的に困っている方を対象としており、以下を満たすことが立替制度の条件です。
- 収入や資産が一定基準以下
- 勝訴の見込みがないとはいえない
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
弁護士費用を払うことが難しい場合、条件を満たしているのであれば立替制度の活用を検討するのもよいでしょう。
分割払いに対応している弁護士事務所に依頼する
弁護士費用の支払いが難しい場合、分割払いに対応している弁護士事務所に依頼し、少額ずつ返していく方法もあります。
分割払いにすることで一時的に大きな費用を支払う必要がなくなるため、トラブル解決に向けて弁護士に依頼しやすくなるでしょう。
分割払いにする場合は、依頼時点で最初の支払いを行い、その後は毎月等分した費用を支払う流れとなります。
分割払いに対応している弁護士事務所は多くありますが、条件や回数は異なるため注意が必要です。
分割払いの上限回数は12回が多く、事件の種類によっては3回や6回の場合もあります。
まずは月々どれくらいの費用なら支払えるかを算出し、それも踏まえたうえで分割払いを相談するとよいでしょう。
まとめ
この記事では、弁護士費用の相場や内訳、安く抑えるポイントを解説しました。
弁護士費用は、契約前の相談料をはじめ、着手金や成功報酬、実費、日当などがかかります。どれくらいの費用になるかは、トラブルの内容や問題の大きさにより変わります。
トラブルが大きくなった後だと解決が難しくなり、弁護士費用も多くかかるため注意しなければなりません。
トラブルが発生した際には、できるだけ早いタイミングで弁護士に依頼し、早期解決を目指すことが費用を抑えるコツです。
費用が払えないという場合も、法テラスの立替制度や分割払いを活用することで支払える場合もあるため、まずは弁護士に相談しましょう。
トラブルや法律に関するお困りごとは、川崎つばさ法律事務所におまかせください。
お金や家族、職場、犯罪、交通事故など、さまざまなトラブルや問題解決の実績があります。当事務所は11人の弁護士が在籍しており、土日夜間も相談可能です。
また、弁護士費用のお支払いは個々の事情に応じて分割払いにも対応しています。まずは、お気軽にご相談ください。